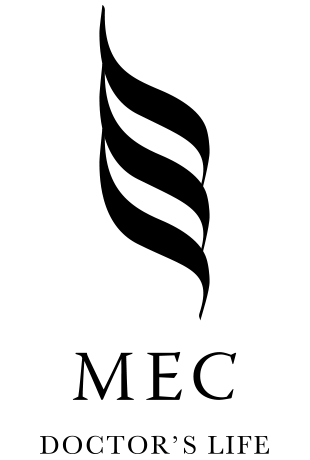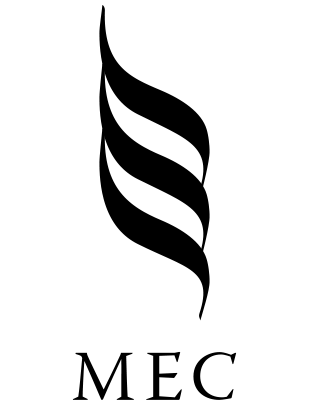最新医師国家試験情報
第120回医師国家試験の施行
-
試験期日
令和8年2月7日(土曜日)及び8日(日曜日)
-
試験地
北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県
※試験会場については受験票送付時に案内する。会場に関する問合せには応じられない。 -
試験内容
臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能
-
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者(大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるものに合格した者に限る。ただし、令和7年4月1日より前に卒業した者は、この規定にかかわらず医師国家試験を受験することができる。)(令和8年3月10日(火曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
- 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの(令和8年3月10日(火曜日)までに実地修練を終える見込みの者を含む。)➡ 詳細はこちらへ
- 外国の医学校を卒業し、または外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)または(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの ➡ 詳細はこちらへ
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの
-
受験手続
-
試験を受けようとする者は次の書類等を提出すること。
ア すべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書
医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第3号書式により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カードまたは住民票、特別永住者については特別永住者証明書または住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。(イ)写真
出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメ-トル、横4センチメ-トルのもので、その裏面に「(イ)」の記号、撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省または医師国家試験運営本部事務所若しくは医師国家試験運営臨時事務所において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出にあたっては、卒業し、若しくは在籍している大学または医師国家試験運営本部事務所若しくは医師国家試験運営臨時事務所において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
※郵送により本人確認を受ける際は、写真が付してある身分証明書等(コピー不可。個人番号カード不可)及び(ウ)とは別に返信用封筒(郵便番号、宛先及び宛名を記載し、身分証明書等の返送に必要な郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの)を同封すること。(ウ)返信用封筒
縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及び宛先を記載し、590円(定形郵便110円+一般書留480円)の郵便切手を貼り付け、書留の表示をすること。イ 4の(1)に該当する者が提出する書類 卒業証明書または卒業見込証明書
この場合、卒業見込証明書を提出した者にあっては、令和8年3月10日(火曜日)午後2時までに卒業証明書を提出すること。ウ 4の(2)に該当する者が提出する書類
医師国家試験予備試験の合格証書の写し(医師国家試験運営本部事務所または医師国家試験運営臨時事務所に合格証書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)または合格証明書及び実地修練施設の長の発行する実地修練を終えたことを証する書面または実地修練を終える見込みであることを証する書面
なお、実地修練を終える見込みであることを証する書面を提出した者にあっては、令和8年3月10日(火曜日)午後2時までに実地修練を終えたことを証する書面を提出すること。
※郵送により原本照合を受ける際は、医師国家試験予備試験の合格証書の原本及び返信用封筒(郵便番号、宛先及び宛名を記載し、合格証書の原本の返送に必要な郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの)を同封すること。エ 4の(3)または(4)に該当する者が提出する書類
医師国家試験受験資格の認定書の写し(医師国家試験運営本部事務所または医師国家試験運営臨時事務所に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
※郵送により原本照合を受ける際は、医師国家試験受験資格の認定書の原本及び返信用封筒(郵便番号、宛先及び宛名を記載し、認定書の原本の返送に必要な郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの)を同封すること。 -
受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア 受験に関する書類は、令和7年11月4日(火曜日)から同年11月28日(金曜日)までに提出すること。
イ 受験に関する書類を郵送する場合の提出先は、医師国家試験運営本部事務所とする。
ウ ただし、下記に掲げる医師国家試験運営臨時事務所においては、受験に関する書類を直接持参する場合について、その提出を受け付けることとする。
北海道 ランスタッド・札幌支店
宮城県 ランスタッド・仙台支店
東京都 ランスタッド・試験監督事業部
愛知県 ランスタッド・名古屋伏見事業所
大阪府 ランスタッド・大阪支店
広島県 ランスタッド・広島支店
香川県 ランスタッド・高松支店
福岡県 ランスタッド・福岡支店
沖縄県 人材派遣センターオキナワエ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前9時から午前12時までと、午後1時から午後5時までとする。
オ 受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。この場合、令和7年11月28日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
カ 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
-
書類の提出については次のことに注意すること。
ア 4の(1)に該当する者で卒業見込証明書を提出したものにあっては、令和8年3月10日(火曜日)午後2時までに卒業証明書の提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。
イ 4の(2)に該当する者で、実地修練を終える見込みであることを証する書面を提出したものにあっては、令和8年3月10日(火曜日)午後2時までに実地修練を終えたことを証する書面の提出がないときは、当該受験は原則として無効とする。
-
受験手数料
ア 受験手数料は、15,300円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
-
受験票の交付
受験票は、郵送により交付する(令和8年1月上旬発送予定)。なお、令和8年1月26日(月曜日)までに受験票が到着しない場合は、医師国家試験運営本部事務所に問い合わせること。
-
-
合格者の発表
試験の合格者は、令和8年3月16日(月曜日)午後2時に厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページにその受験地及び受験番号を掲載して発表する。
-
受験に伴う配慮
視覚、聴覚、音声機能または言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、令和7年10月1日(水曜日)までに医師国家試験運営本部事務所に「国家試験の受験に伴う配慮事項申請書」を用いて申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
-
手続及び問い合わせ先
- 試験に関する手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。
医師国家試験運営本部事務所
東京都江東区有明3丁目6番11号
TFTビル東館7階
郵便番号 135-0063
電話番号 03(5579)6903 -
5の(2)のアの期間に、受験に関する書類を直接持参する場合の提出先は下記の試験地を管轄する医師国家試験運営臨時事務所とする。
※医師国家試験運営臨時事務所での電話受付は行っておりません。電話での問い合わせは医師国家試験運営本部事務所(03-5579-6903)へお願いします。
試験地 医師国家試験運営臨時事務所 北海道 ランスタッド・札幌支店 国家試験係
北海道札幌市中央区北四条西4丁目1番3号
伊藤ビル5階宮城県 ランスタッド・仙台支店 国家試験係
宮城県仙台市青葉区中央1丁目2番3号
仙台マークワン15階東京都
新潟県ランスタッド・試験監督事業部 国家試験係
東京都江東区有明3丁目6番11号
TFTビル東館7階愛知県
石川県ランスタッド・名古屋伏見事業所 国家試験係
愛知県名古屋市中区栄1丁目24番15号
プライム名古屋伏見ビル2階大阪府 ランスタッド・大阪支店 国家試験係
大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号
ハービスENTオフィスタワー18階広島県 ランスタッド・広島支店 国家試験係
広島県広島市中区本通6番11号
明治安田生命広島本通ビル8階香川県 ランスタッド・高松支店 国家試験係
香川県高松市番町1丁目6番8号
高松興銀ビル8階福岡県
熊本県ランスタッド・福岡支店 国家試験係
福岡県福岡市中央区天神1丁目6番8号
天神ツインビル9階沖縄県 人材派遣センターオキナワ 国家試験係
沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号
琉球リース総合ビル9階 - 試験に関する手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。
-
受験願書等の請求方法について(受験願書配布時期 令和7年10月中旬以降)
受験願書を含め、受験手続きに必要な書類は各大学において入手する方法の他に、下記の方法により、医師国家試験運営本部事務所若しくは医師国家試験運営臨時事務所または厚生労働省からも入手することができる。
- 郵送による請求
下記要領1~3により、医師国家試験運営本部事務所(請求先住所等は8の(1)のとおり)または厚生労働省医政局医事課試験免許室宛て請求すること。なお、手元に到着するまで、最低1週間程度かかることから、早めに請求すること。要領1 返信用封筒の作成
・封筒の大きさ
角2(縦33cm×横24cm、A4版の用紙が折らずに入るもの)
・封筒表面には下記(1)~(3)を必ず記載すること。
(1)返信先(請求者)の郵便番号
(2) 〃 住所
(3) 〃 氏名*記載漏れ等がある場合には返信できないこともあるので注意すること。
・封筒に180円切手を貼付すること(普通郵便物、定形外郵便物、100gまで)(1部、60g程度)。
なお、速達郵便で請求する場合は480円切手を貼付すること。
要領2 願書請求用紙の作成
・願書請求用紙を印刷し、必要事項を記載
*以下3点を記載したメモ用紙でも差し支えないが、記載漏れ等がある場合には返信できないこともあるので注意すること。
・請求を希望する職種(医師)
・必要部数
・請求者情報(氏名・連絡先(自宅電話番号、携帯番号等))
要領3 要領1により作成した返信用封筒及び要領2により作成した請求用紙の郵送
要領1により作成した返信用封筒と要領2により作成した請求用紙を封筒に入れ、医師国家試験運営本部事務所または厚生労働省医政局医事課試験免許室あて請求すること。作成した返信用封筒は折り曲げて差し支えない。郵送する封筒の大きさは問わない。ただし、切手料金不足があった場合は、受領できないことがあるので注意すること(普通郵便物、定形郵便物、50gまで、110円切手)。
以下の資料を送付するので、受領後、送付物を確認すること。(1)受験願書
(2)受験要領
(3)受験写真用台紙 - 窓口での請求
医師国家試験運営臨時事務所(所在地は8の(2)のとおり)または厚生労働省の受付窓口(医政局医事課試験免許室)にて、希望する職種(医師)について必要部数を請求すること。
ただし、庁舎へ入館する際に写真付身分証の提示が必要になる場合がある。また、中央合同庁舎第5号館に入館の際は訪問先の担当職員への事前登録と、写真付身分証が必要になるので注意すること。
窓口は行政機関の休日を除く、午前9時から午前12時までと午後1時から午後5時までであること。
また、駐車場は利用できないため他の交通機関を利用すること。
- 郵送による請求
-
災害等の対応について
災害等によって国家試験の時間等に変更が生じた場合は、厚生労働省ホームページに掲載する。
-
試験委員
第120回医師国家試験 試験委員(令和7年7月1日発表)氏名 委員長 福島 裕之 副委員長 齋藤 登
委員 赤井 靖宏 赤坂 真奈美 荒川 敏 石浦 浩之 石木 寛人 石毛 美夏 石島 旨章 石丸 裕康 伊藤 智範 稲森 正彦 犬飼 道雄 井上 茂 井上 透 井濱 容子 今村 英仁 岩瀬 明 上野 祐司 宇於崎 宏 臼井 智彦 大塚 崇 大塚 麻樹 大平 善之 大脇 哲洋 岡山 雅信 小川 弘子 尾島 俊之 小田原 俊成 小野 政徳 加治 建 金子 祐子 嘉山 智大 川田 一郎 河内 泉 川浪 大治 菊池 健太郎 北島 美香 木村 孝穂 具 芳明 熊木 天児 栗田 浩樹 古和 久朋 近藤 英治 坂上 拓郎 櫻井 大樹 佐々木 陽典 佐田 憲映 佐々 直人 佐野 厚 島 友子 島村 和男 杉浦 一充 鈴木 映二 鈴木 恭子 鈴木 秀海 鈴木 麻衣 鈴木 亮 髙尾 正樹 高月 晋一 高橋 広喜 高橋 宏典 竹島 太郎 田中 京子 谷垣 伸治 多林 孝之 筑田 博隆 知花 なおみ 辻 哲也 土屋 静馬 時松 一成 冨田 尚希 中川 義久 中島 歩 中村 京太 中村 桂子 名越 究 西山 充 野口 輝夫 野口 佳裕 野崎 実穂 野村 恭子 馳 亮太 長谷川 俊史 秦 広樹 馬場 香子 藤野 善久 北條 麻理子 本多 奈美 牧野 真太郎 三井 貴彦 三原 弘 宮田 靖志 武笠 晃丈 森 龍彦 森川 守 森下 英理子 守谷 俊 八重樫 牧人 安岡 秀剛 安田 真之 八谷 寛 八尋 英二 山口 泰弘 山﨑 悦子 山田 隆之 山本 俊幸 横堀 將司 横山 みなと 吉澤 定子 萬 知子 渡辺 昌文 ※五十音順(敬称略)
※個人情報保護の観点から、所属、担当回、専門領域は掲載いたしません。
※ 出典 厚生労働省HP・「医師国家試験の施行について」(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/ishi/※参考 厚生労働省HP・「令和6年版医師国家試験出題基準について」(厚生労働省)
医師国家試験出題基準
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000128981_00001.html
第120回医師国家試験 合格発表
■第120回合格発表日
発表後に更新いたします。
■第120回合格率
発表後に更新いたします。
■第120回合格基準
発表後に更新いたします。
第120回医師国家試験 大学別合格率
発表後に更新いたします。
第120回医師国家試験 概要
発表後に更新いたします。
医師国家試験とは
受験資格
医師国家試験は、日本で医師として働くために必要な医師免許を取得するための国家試験です。大学で6年間の医学部課程を修了し、卒業資格を得た人が受験できます。
また、海外の医学校を卒業した人、海外で医師免許を取得した人は、厚生労働省の「医師国家試験受験資格認定」の審査を通過することで、医師国家試験を受験することができます。
試験日程
試験は年に1度、2月の「土日2日間」の日程で行われます。
受験手続
医師国家試験へ出願するには、出願書類を用意し、11月中に「医師国家試験運営本部事務所」への提出することが必要です。
現役生は、各大学が書類を手配や出願を取りまとめてくれるケースが多いですが、既卒生などの個人申込の場合は自分で書類の手配や出願をする必要があります。
受験票の交付は、現役生は大学がとりまとめて受領し、個人申込の場合は1月下旬に郵送されてきます。
合格率・合格基準
<合格率>
約10,000人が受験し、その合格率は例年90%前後です。
<合格基準>
医師国家試験合格のためには以下3項目の基準を満たす必要があります。
- 必修問題は80%以上の得点(絶対基準)
- 必修を除く一般/臨床問題の得点がボーダー以上(相対基準)
- 禁忌肢の選択が基準数以下(絶対基準)
必修問題を80%以上の得点とすること、禁忌肢の選択を基準数以内におさえること、必修を除いた一般/臨床問題をボーダー以上得点することではじめて医師国家試験に合格となります。
試験概要
2日間で合計400問、試験時間計13時間40分です。
1月に交付される受験票にて、その年の時間割を確認できます。
問題構成
問題形式は、医師に最低限必要な知識が問われる「必修」、疾病ごとの知識を問われる「各論」、疾患を跨いで横断的な知識が問われる「総論」の3つに分類され、それぞれ症例ではなくあるキーワードについての知識が問われる「一般問題」と、症例文を読み、それについての所見や対応が問われる「臨床問題」から構成されます。
<必修>
50問×2日間の計100問。一般問題25問、臨床問題25問で構成されます。
基本的知識だからこそ、合格ライン8割(得点160点/200点)という絶対基準が設定されています。
<各論>
75問×2日間の計150問。一般問題15問、臨床問題60問で構成されます。
疾患の症状や検査、診断、治療などのテーマ。科目別、臓器別に分類され、個々の疾患に対する知識が問われます。
<総論>
75問×2日間の計150問。一般問題35問、臨床問題40問で構成されます。
解剖、生理、症候、検査、治療、診察、保険医学、法律といった、医学・医療全体に関わるテーマ。基礎的な知識と各科目を横断する幅広い知識が問われます。
試験の傾向
医師国家試験は、医師に求められるものの変化にあわせて出題傾向も変化してきました。第118回からは新しいガイドラインとなり、近年社会的に注目されている概念や、実臨床を意識した問題からの出題が見られるなど、新しい知識を求められるケースも多くなっています。
医師国家試験の勉強法についてお困りごとのある方は、是非メックのサービスをご利用ください。
第119回
医師国家試験情報はこちら
第119回医師国家試験 合格発表
■第119回合格発表日
2025年3月14日(金)
■第119回合格率
受験者数: 10,282名 > 合格者数:9,486名 > 合格率: 92.3%
■第119回合格基準
第119回医師国家試験の合格基準は、必修問題は一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、必修問題を除いた一般問題及び臨床実地問題については、各々1問1点とした上で、(1)から(3)のすべての合格基準を満たした者を合格とする。
|
(1) 必修問題を除いた一般問題 および臨床実地問題 |
221点以上/300点 |
|---|---|
| (2) 必修問題 | 160点以上/200点 |
| (3) 禁忌肢問題選択数 | 3問以下 |
第119回医師国家試験 大学別合格率
| 大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者数 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 出願者数 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 出願者数 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
| 北海道大学 | 116 | 114 | 106 | 93.0% | 103 | 102 | 100 | 98.0% | 13 | 12 | 6 | 50.0% |
| 旭川医科大学 | 129 | 128 | 119 | 93.0% | 114 | 114 | 111 | 97.4% | 15 | 14 | 8 | 57.1% |
| 弘前大学 | 148 | 146 | 137 | 93.8% | 129 | 128 | 124 | 96.9% | 19 | 18 | 13 | 72.2% |
| 東北大学 | 156 | 154 | 148 | 96.1% | 149 | 149 | 145 | 97.3% | 7 | 5 | 3 | 60.0% |
| 秋田大学 | 138 | 137 | 131 | 95.6% | 132 | 131 | 128 | 97.7% | 6 | 6 | 3 | 50.0% |
| 山形大学 | 113 | 112 | 104 | 92.9% | 107 | 107 | 102 | 95.3% | 6 | 5 | 2 | 40.0% |
| 筑波大学 | 146 | 142 | 137 | 96.5% | 142 | 138 | 134 | 97.1% | 4 | 4 | 3 | 75.0% |
| 群馬大学 | 117 | 115 | 110 | 95.7% | 112 | 111 | 106 | 95.5% | 5 | 4 | 4 | 100.0% |
| 防衛医科大学校 | 87 | 81 | 76 | 93.8% | 85 | 79 | 75 | 94.9% | 2 | 2 | 1 | 50.0% |
| 千葉大学 | 132 | 130 | 125 | 96.2% | 127 | 126 | 123 | 97.6% | 5 | 4 | 2 | 50.0% |
| 東京大学 | 122 | 120 | 112 | 93.3% | 108 | 106 | 103 | 97.2% | 14 | 14 | 9 | 64.3% |
| 東京科学大学 | 103 | 103 | 96 | 93.2% | 96 | 96 | 93 | 96.9% | 7 | 7 | 3 | 42.9% |
| 新潟大学 | 140 | 137 | 127 | 92.7% | 133 | 130 | 124 | 95.4% | 7 | 7 | 3 | 42.9% |
| 富山大学 | 120 | 116 | 109 | 94.0% | 111 | 107 | 105 | 98.1% | 9 | 9 | 4 | 44.4% |
| 金沢大学 | 134 | 126 | 123 | 97.6% | 122 | 117 | 117 | 100.0% | 12 | 9 | 6 | 66.7% |
| 福井大学 | 129 | 126 | 124 | 98.4% | 121 | 118 | 118 | 100.0% | 8 | 8 | 6 | 75.0% |
| 山梨大学 | 133 | 131 | 118 | 90.1% | 126 | 124 | 112 | 90.3% | 7 | 7 | 6 | 85.7% |
| 信州大学 | 135 | 134 | 125 | 93.3% | 126 | 126 | 121 | 96.0% | 9 | 8 | 4 | 50.0% |
| 岐阜大学 | 116 | 116 | 111 | 95.7% | 108 | 108 | 107 | 99.1% | 8 | 8 | 4 | 50.0% |
| 浜松医科大学 | 121 | 120 | 117 | 97.5% | 115 | 114 | 112 | 98.2% | 6 | 6 | 5 | 83.3% |
| 名古屋大学 | 120 | 120 | 112 | 93.3% | 115 | 115 | 110 | 95.7% | 5 | 5 | 2 | 40.0% |
| 三重大学 | 130 | 128 | 124 | 96.9% | 119 | 119 | 119 | 100.0% | 11 | 9 | 5 | 55.6% |
| 滋賀医科大学 | 138 | 130 | 123 | 94.6% | 130 | 122 | 118 | 96.7% | 8 | 8 | 5 | 62.5% |
| 京都大学 | 114 | 112 | 100 | 89.3% | 102 | 101 | 94 | 93.1% | 12 | 11 | 6 | 54.5% |
| 大阪大学 | 133 | 131 | 122 | 93.1% | 124 | 124 | 120 | 96.8% | 9 | 7 | 2 | 28.6% |
| 神戸大学 | 130 | 128 | 116 | 90.6% | 120 | 118 | 111 | 94.1% | 10 | 10 | 5 | 50.0% |
| 鳥取大学 | 119 | 117 | 109 | 93.2% | 106 | 106 | 100 | 94.3% | 13 | 11 | 9 | 81.8% |
| 島根大学 | 113 | 112 | 101 | 90.2% | 104 | 104 | 97 | 93.3% | 9 | 8 | 4 | 50.0% |
| 岡山大学 | 125 | 123 | 116 | 94.3% | 114 | 113 | 107 | 94.7% | 11 | 10 | 9 | 90.0% |
| 広島大学 | 123 | 123 | 108 | 87.8% | 113 | 113 | 107 | 94.7% | 10 | 10 | 1 | 10.0% |
| 山口大学 | 132 | 132 | 121 | 91.7% | 121 | 121 | 115 | 95.0% | 11 | 11 | 6 | 54.5% |
| 徳島大学 | 127 | 127 | 115 | 90.6% | 112 | 112 | 108 | 96.4% | 15 | 15 | 7 | 46.7% |
| 香川大学 | 119 | 118 | 106 | 89.8% | 111 | 110 | 100 | 90.9% | 8 | 8 | 6 | 75.0% |
| 愛媛大学 | 125 | 125 | 110 | 88.0% | 116 | 116 | 104 | 89.7% | 9 | 9 | 6 | 66.7% |
| 高知大学 | 115 | 115 | 108 | 93.9% | 101 | 101 | 99 | 98.0% | 14 | 14 | 9 | 64.3% |
| 九州大学 | 124 | 119 | 106 | 89.1% | 103 | 100 | 95 | 95.0% | 21 | 19 | 11 | 57.9% |
| 佐賀大学 | 107 | 104 | 101 | 97.1% | 102 | 100 | 98 | 98.0% | 5 | 4 | 3 | 75.0% |
| 長崎大学 | 135 | 131 | 123 | 93.9% | 119 | 118 | 112 | 94.9% | 16 | 13 | 11 | 84.6% |
| 熊本大学 | 131 | 129 | 119 | 92.2% | 121 | 121 | 115 | 95.0% | 10 | 8 | 4 | 50.0% |
| 大分大学 | 112 | 110 | 102 | 92.7% | 104 | 104 | 101 | 97.1% | 8 | 6 | 1 | 16.7% |
| 宮崎大学 | 144 | 144 | 132 | 91.7% | 136 | 136 | 128 | 94.1% | 8 | 8 | 4 | 50.0% |
| 鹿児島大学 | 115 | 111 | 105 | 94.6% | 111 | 107 | 103 | 96.3% | 4 | 4 | 2 | 50.0% |
| 琉球大学 | 121 | 121 | 117 | 96.7% | 115 | 115 | 112 | 97.4% | 6 | 6 | 5 | 83.3% |
| 札幌医科大学 | 121 | 121 | 113 | 93.4% | 115 | 115 | 110 | 95.7% | 6 | 6 | 3 | 50.0% |
| 福島県立医科大学 | 140 | 139 | 135 | 97.1% | 133 | 133 | 131 | 98.5% | 7 | 6 | 4 | 66.7% |
| 横浜市立大学 | 88 | 88 | 86 | 97.7% | 85 | 85 | 84 | 98.8% | 3 | 3 | 2 | 66.7% |
| 名古屋市立大学 | 100 | 100 | 95 | 95.0% | 99 | 99 | 94 | 94.9% | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 京都府立医科大学 | 105 | 103 | 99 | 96.1% | 98 | 98 | 95 | 96.9% | 7 | 5 | 4 | 80.0% |
| 大阪公立大学 | 105 | 105 | 101 | 96.2% | 99 | 99 | 98 | 99.0% | 6 | 6 | 3 | 50.0% |
| 奈良県立医科大学 | 119 | 118 | 109 | 92.4% | 107 | 106 | 103 | 97.2% | 12 | 12 | 6 | 50.0% |
| 和歌山県立医科大学 | 120 | 115 | 102 | 88.7% | 105 | 101 | 92 | 91.1% | 15 | 14 | 10 | 71.4% |
| 岩手医科大学 | 136 | 132 | 121 | 91.7% | 122 | 120 | 115 | 95.8% | 14 | 12 | 6 | 50.0% |
| 自治医科大学 | 135 | 135 | 134 | 99.3% | 135 | 135 | 134 | 99.3% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨協医科大学 | 138 | 133 | 119 | 89.5% | 131 | 126 | 114 | 90.5% | 7 | 7 | 5 | 71.4% |
| 埼玉医科大学 | 144 | 143 | 135 | 94.4% | 136 | 136 | 130 | 95.6% | 8 | 7 | 5 | 71.4% |
| 杏林大学 | 139 | 136 | 129 | 94.9% | 132 | 130 | 126 | 96.9% | 7 | 6 | 3 | 50.0% |
| 慶應義塾大学 | 116 | 115 | 110 | 95.7% | 108 | 108 | 107 | 99.1% | 8 | 7 | 3 | 42.9% |
| 順天堂大学 | 142 | 142 | 139 | 97.9% | 139 | 139 | 136 | 97.8% | 3 | 3 | 3 | 100.0% |
| 昭和大学 | 113 | 113 | 102 | 90.3% | 107 | 107 | 99 | 92.5% | 6 | 6 | 3 | 50.0% |
| 帝京大学 | 152 | 150 | 143 | 95.3% | 141 | 140 | 138 | 98.6% | 11 | 10 | 5 | 50.0% |
| 東京医科大学 | 120 | 109 | 104 | 95.4% | 117 | 106 | 102 | 96.2% | 3 | 3 | 2 | 66.7% |
| 東京慈恵会医科大学 | 114 | 113 | 109 | 96.5% | 105 | 105 | 104 | 99.0% | 9 | 8 | 5 | 62.5% |
| 東京女子医科大学 | 120 | 120 | 110 | 91.7% | 111 | 111 | 103 | 92.8% | 9 | 9 | 7 | 77.8% |
| 東邦大学 | 120 | 120 | 113 | 94.2% | 109 | 109 | 107 | 98.2% | 11 | 11 | 6 | 54.5% |
| 日本大学 | 131 | 118 | 109 | 92.4% | 123 | 111 | 104 | 93.7% | 8 | 7 | 5 | 71.4% |
| 日本医科大学 | 121 | 120 | 113 | 94.2% | 119 | 119 | 113 | 95.0% | 2 | 1 | 0 | 0.0% |
| 北里大学 | 138 | 124 | 113 | 91.1% | 133 | 119 | 110 | 92.4% | 5 | 5 | 3 | 60.0% |
| 東海大学 | 104 | 103 | 96 | 93.2% | 95 | 94 | 93 | 98.9% | 9 | 9 | 3 | 33.3% |
| 聖マリアンナ医科大学 | 118 | 113 | 102 | 90.3% | 115 | 110 | 99 | 90.0% | 3 | 3 | 3 | 100.0% |
| 金沢医科大学 | 146 | 131 | 122 | 93.1% | 126 | 111 | 105 | 94.6% | 20 | 20 | 17 | 85.0% |
| 愛知医科大学 | 117 | 107 | 101 | 94.4% | 110 | 101 | 99 | 98.0% | 7 | 6 | 2 | 33.3% |
| 藤田医科大学 | 113 | 110 | 107 | 97.3% | 108 | 106 | 104 | 98.1% | 5 | 4 | 3 | 75.0% |
| 大阪医科薬科大学 | 103 | 100 | 97 | 97.0% | 98 | 95 | 93 | 97.9% | 5 | 5 | 4 | 80.0% |
| 関西医科大学 | 157 | 147 | 130 | 88.4% | 144 | 134 | 121 | 90.3% | 13 | 13 | 9 | 69.2% |
| 近畿大学 | 133 | 127 | 116 | 91.3% | 126 | 120 | 110 | 91.7% | 7 | 7 | 6 | 85.7% |
| 兵庫医科大学 | 110 | 110 | 109 | 99.1% | 109 | 109 | 108 | 99.1% | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 川崎医科大学 | 145 | 132 | 114 | 86.4% | 132 | 120 | 105 | 87.5% | 13 | 12 | 9 | 75.0% |
| 久留米大学 | 139 | 129 | 107 | 82.9% | 124 | 115 | 97 | 84.3% | 15 | 14 | 10 | 71.4% |
| 福岡大学 | 119 | 112 | 101 | 90.2% | 99 | 92 | 87 | 94.6% | 20 | 20 | 14 | 70.0% |
| 産業医科大学 | 116 | 109 | 103 | 94.5% | 115 | 108 | 102 | 94.4% | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 東北医科薬科大学 | 105 | 96 | 88 | 91.7% | 100 | 91 | 84 | 92.3% | 5 | 5 | 4 | 80.0% |
| 国際医療福祉大学 | 131 | 127 | 127 | 100.0% | 130 | 126 | 126 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 認定及び予備試験 | 324 | 319 | 172 | 53.9% | 192 | 191 | 114 | 59.7% | 132 | 128 | 58 | 45.3% |
| 総計 | 10,544 | 10,282 | 9,486 | 92.3% | 9,717 | 9,507 | 9,029 | 95.0% | 827 | 775 | 457 | 59.0% |
第119回医師国家試験 概要
実施日:令和7年2月8日(土曜日)及び9日(日曜日)の2日間実施。
1日目
| A | 9:30~12:15/165分 | 75問 | 各論 | 一般:15問・臨床:60問 (5肢1択:66、5肢2択:8、計算:1) |
|---|---|---|---|---|
| B | 13:35~15:10/95分 | 50問 | 必修 | 一般:25問・臨床:15問・長文(2連問×5):10問 (5肢1択:50) |
| C | 16:00~18:30/150分 | 75問 | 総論 | 一般:35問・臨床:25問・長文(3連問×5):15問 (5肢1択:68、5肢2択:4、5肢3択:1、計算:2) |
2日目
| D | 9:30~12:15/165分 | 75問 | 各論 | 一般:15問・臨床:60問 (5肢1択:65、5肢2択:8、5肢3択:2) |
|---|---|---|---|---|
| E | 13:35~15:10/95分 | 50問 | 必修 | 一般:25問・臨床:15問・長文(2連問×5):10問 (5肢1択:50) |
| F | 16:00~18:30/150分 | 75問 | 総論 | 一般:35問・臨床:25問・長文(3連問×5):15問 (5肢1択:58、5肢2択:14、5肢3択:2、計算:1) |
試験会場
| 試験地 | 試験場 |
|---|---|
| 北海道 | 北海道:TKPガーデンシティ札幌駅前 |
| 東北 | 宮城:仙台卸商センター サンフェスタ・卸町会館 |
| 関東信越 |
東京:大正大学巣鴨キャンパス 東京:帝京平成大学中野キャンパス 新潟:日本歯科大学新潟生命歯学部 |
| 東海北陸 |
愛知:愛知学院大学日進キャンパス 石川:石川県青少年総合研修センター |
| 近畿 | 大阪:大阪電気通信大学寝屋川キャンパス |
| 中国 | 広島:安田女子大学 |
| 四国 | 香川:サンメッセ香川 |
| 九州 |
福岡:第一薬科大学 熊本:熊本保健科学大学 |
| 沖縄 | 沖縄:琉球大学 千原キャンパス 共通教育棟 |
第119回医師国家試験 総評
第119回医師国家試験が終了いたしました。受験生の皆様、2日間大変お疲れ様でした。
近年の国試は合格基準が年々上昇しており、一般・臨床(総論・各論)の得点率で117回は74.6%、118回は76.7%でした。この流れから「119回は、一般・臨床でも必修の8割と同程度になるのではないか」といった懸念もありました。しかしながら、今回は骨太な出題が多く、結果的にはやや難化傾向となり、合格基準は前回に及ばないものと予測されます。
近年の国試は「新しい治療や疾患・近年注目されている概念」と「実臨床で使える知識」を問う問題が増加しているという特徴がありますが、今回は特に前者の出題が目立ちました。非ST上昇型心筋梗塞(A31)、左室駆出率の保たれた心不全〈HFpEF〉(A44)、ネーザルハイフロー療法(A72)、ヘパリン起因性血小板減少症(D8)など、なんとなく聞いたことはあったり、卒業試験や模擬試験で出題されていたりはするが、過去の国試では明確に問われてこなかったテーマが積極的に出題されていました。一方で、de Quervain病(A39)や、肺過誤腫(D16)などといった、昔出題されていたものの近年めっきり見なくなっていた疾患もリバイバルされており、隙のない学習が要求されていました。
今回の国試を難しくしていた要因として、選択肢自体はその疾患に対して行われ得るが、問われている症例で適応できるかという判断までを問う問題が多かったということも挙げられます。慢性膵炎(A58)では脂肪制限も行うことがあるが、この症例では腹痛を訴えていないため行わない。原発性胆汁性胆管炎(D36)では肝生検が有用な検査だが、この症例では腹水貯留のためできない。といった、目の前の患者に照らした臨床判断が求められる出題があり、治療をただ横並びに覚えるだけでは対応できず、受験生にとっては難易度は高かったと思われます。
さて、どうしても解きづらい難問に注目しがちですが、大半の問題はやはり基本的な内容、過去問ベースの問題であることに変わりはありません。解ける問題を確実に解くことが重要になります。潰瘍性大腸炎に特徴的な所見(A7)や、アニオンギャップが開大する病態(F34)などはCBT的な基礎知識であり落としたくないところです。下咽頭癌の診断(D68)、前置癒着胎盤の診断(D74)などは、過去問の画像がそのまま使われており、画像問題が苦手でも過去問演習をしていれば正解できます。全身性エリテマトーデス〈SLE〉で胎児に影響を与える可能性がある自己抗体(D22)や、無痛性甲状腺炎患者への方針(D23)など、過去問とほぼ同じ問題も多く出題されており、しっかり過去問演習をできていれば即答できたはずです。
①出題形式
(1)問題タイプ別の変化
| 第119回 | 第118回 | 第117回 | 第116回 | 第115回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5肢1択 | 357 | 355 | 342 | 334 | 338 |
| 5肢2択 | 34 | 29 | 35 | 44 | 51 |
| 5肢3択 | 5 | 11 | 18 | 18 | 8 |
| 多選択肢問題※ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 計算問題 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
※6肢以上の選択肢数の問題。
-
複数正答(5肢2択、5肢3択)の出題は39問で、国試が400問になった112回以降で初めて出題数が40問未満となりました。特に5肢3択問題の出題数は5問に留まり、112回以降で最も少ない出題数でした。
-
英語問題は全文英語の問題のみが出題され、118回から1問増加し、5問出題されました(各論一般・A03、必修臨床・B35、総論一般・C18、F19、F25)。
-
計算問題(0~9の数字を選ばせる問題)の出題数は118回と同様に4問出題されました(各論一般・A75、総論臨床・C74、C75、F75)。
-
6肢以上の多選択肢問題は出題されませんでした。1問も出題されなかったのは114回以来です。
-
下線部5択問題は118回より6問増加し、15問出題されました。
-
臨床問題の設問内容別では、診断を問う問題が減少し(119回39問、118回51問)、治療・対応を問う問題が増加しました(119回102問、118回94問)。
-
正答として「誤り」を選ばせる問題は46問出題され、117回から2年連続で減少しました(118回53問、117回69問)。
-
問題冊子に表やグラフ、イラストなどが図示されている問題は118回と同様に9問出題されました。
(2)画像問題数の変化
| 第119回 | 第118回 | 第117回 | 第116回 | 第115回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 画像問題数※ | 97 | 89 | 110 | 99 | 98 |
| 画像点数 | 152 | 138 | 179 | 146 | 171 |
※別冊冊子に画像が提示された問題。
-
画像問題数は97問で、118回から8問増加しました(118回89問)。
-
画像問題1問あたりの画像点数は1.57点で、118回とほぼ同等でした(118回1.55点)。
-
画像5択問題は118回と同様に7問出題されました。
(3)画像点数の変化
| 第119回 | 第118回 | 第117回 | 第116回 | 第115回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部CT | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 頭部MRI・MRA | 6 | 4 | 13 | 1 | 8 |
| 胸部CT | 15 | 8 | 13 | 11 | 15 |
| 胸部エックス線 | 14 | 8 | 11 | 16 | 13 |
| 心電図 | 7 | 7 | 8 | 4 | 11 |
| 心エコー | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 腹部CT | 6 | 5 | 11 | 12 | 10 |
| 腹部エックス線 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 腹部超音波写真 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 消化管内視鏡 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 染色標本 | 7 | 6 | 11 | 14 | 10 |
| 外観 | 21 | 18 | 22 | 15 | 23 |
| 器具・手技 | 0 | 15 | 6 | 5 | 6 |
| その他CT・MRI・エックス線 | 27 | 18 | 29 | 23 | 15 |
| その他 | 38 | 31 | 33 | 28 | 46 |
| 合計 | 152 | 138 | 179 | 146 | 171 |
-
画像点数は152点で、118回から14点増加しました(118回138点)。
-
種類ごとの点数で大きく増加がみられたのは胸部CT(119回15点、118回8点)、胸部エックス線写真(119回14点、118回8点)でした。減少となったのは頭部CT(119回2点、118回5点)、心エコー(119回1点、118回5点)、器具・手技の写真(119回0点、118回18点)でした。
(4)その他
なし
②出題科目
(1)内科系
結核(D72)、梅毒(F66~68)、心筋梗塞(A31、F69~71)、肺塞栓症(A70)など、毎回必ず出題される疾患についてはきちんと出題されていましたが、結核は治療効果の判定に用いられる検査が問われており、心筋梗塞は非ST上昇型と右室梗塞、肺塞栓症は慢性型など、例年の典型的な問題に比べると一ひねり加えられた出題となっているのが特徴です。頻出疾患ではあるものの、今回これらの問題で確実に得点するのは意外と難しかったのではないでしょうか。
(2)公衆衛生
2024年は健康日本21(第三次)の開始年であり、目標について出題されました(C1)。SDGs(C24)など、近年のトピックスが問われた一方で、薬害エイズ事件(C27)のようなかなり古い社会問題も出題されており、幅広い知識が要求されました。ワクチンの接種スケジュール(C53)は従来の乳児期だけでなく小学校入学前に接種するものが問われており、厳密な接種のタイミングまで覚えておかなければ解けないのは酷でしょう。インフルエンザの学童の出席停止期間(C52)は例年より一歩踏み込んだ、実際の登校可能日を問う形式となっており、ただ出席停止基準の文章を機械的に覚えるだけでは対応できない、より実地的な問題となっています。
公衆衛生といえばの計算問題ですが、人口にかかわる計算は珍しく出題がなく、検査後確率の計算(E39)のみでした。疫学・統計分野は計算問題だけでなく統計解析手法(F9)など高度な統計知識が必要な難問が出題されており、今後はより深い学習が求められるでしょう。
(3)マイナー
マイナーは多くの学生にとって勉強が手薄になる分野であるため、そもそも難しく感じる学生が多いと思われますが、出題傾向は内科と大きく異なることはありません。囊腫の診断(F50)など、過去問通りの問題を堅実に得点したいところです。一方で、肩関節脱臼(A9)や表皮下水疱の鑑別(D63)などの難問も目立ちました。ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術の術前説明(D52)などの臨床現場の知識を問う問題もあり、内科と同様に病棟実習での知識習得が要求されています。
(4)その他の科目
-
産婦人科、小児科は例年通り
正常妊娠経過(F41)、回旋異常(F47)、微弱陣痛の対応(C38)など、例年通り正常の妊娠経過についての把握を求める出題が多くみられました。基礎知識をきちんと身に付けていれば解けますが、問題文をじっくり読んで異常がないか一つずつ判断していく必要があるので、十分に時間をかけて臨みたいところです。
小児科は例年に比べると染色体や遺伝学、先天異常に関する問題が目立ち、最も多くの遺伝子を含む染色体(E17)などの難問も散見されました。 -
救急、外傷の出題が目立つ
珍しく明らかな麻酔科の出題はなく、放射線科についても定位放射線照射の適応(F11)くらいで、数は少なかったです。一方で外科、周術期管理の問題は、腹腔鏡下手術の周術期管理(D3)、周術期血糖コントロール(F46)、ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術の術前説明(D52)など、疾患を問わず多く出題されていました。今回の大きな特徴は救急、特に外傷に関する問題が多かったことです。その中でも、皮膚開放創に用いることができる消毒薬(E18)、感染創において創部を消毒する前に行うもの(F59)など、創部の処置にかかわる知識が複数問われていたのが印象的でした。
③一般問題
一般問題の多く占める公衆衛生は、ICFにおける会社の提案に相当するもの(C41)などの難問もあるものの、例年に比べると細かい統計の解釈などの出題は少なかった印象です。
一方で内科・マイナー分野での難問が目立ちました。心室中隔を灌流している冠動脈(C33)、大腿静脈の周辺解剖(F2)など、解剖の問題も難易度が高く、脳出血の好発部位(A3)では極めて専門的な解剖用語の英語が要求されました。また、特筆すべきは計算問題で、公衆衛生分野で比較的少なかった分、イン・アウトバランスの計算(A75)や、Naの欠乏量の計算(F75)など、体液量にかかわる計算問題が極めて難問でした。
④臨床問題
新しい疾患や知らない疾患が出題されたわけではないのですが、微妙な臨床判断を求める問題が多かったと感じました。子宮頸癌のステージに応じた治療(A55)、肺癌のステージに応じた治療(A62)など、悪性腫瘍のステージに応じた治療を問う問題のみならず、低ナトリウム血症にまず行うべき対応(D53)なども正確な診断が困難で、判断に迷ったのではないでしょうか。原発性胆汁性胆管炎の診断のために行うべき検査(D36)、露出血管を伴わない消化性潰瘍への対応(F65)なども、その疾患に対して行うものが複数選択肢にあることから、いわゆる「割れ問」となっています。
⑤必修問題
時折難問もみられるものの、全体としては正答率8割の確保が難しい内容ではなく、例年通りと感じました。上部消化管内視鏡実施時の体位(B15)など、臨床現場の知識を要求する問題があるのは毎年のことですが、長時間の砕石位による合併症(E14)などの必修レベルとは思えない問題も出題されています。倫理に関する問題は常識的なものや、明らかな誤りの選択肢が含まれていることが多いですが、今回出題された医療倫理の4原則に含まれないもの(E3)などは、どの選択肢もありそうな内容で難しかったと思います。一般問題に難問が比較的多く、臨床問題はスタンダードな内容が多いと感じました。アルコール離脱せん妄で認められる所見(B47)などは、問題文をきちんと読解する必要があるので、慌てずに読むことが大切です。薬剤性心筋症の原因薬剤の知識(E44)も必修レベルではないように感じますが、過去に113F-74(総論)で関連知識が出題されている内容であり、必修かそうでないかを意識せずに学習しておくことも重要です。
⑥メックの医師国家試験対策
難易度は118回に比べると全体的に上昇したものの、近年の国試としては標準的なレベルに戻ってきた印象でした。
特に一般問題は、基礎医学的な知識も踏まえて問われるなど、医学部6年間で習得すべき知識の有無を判定する、国試の意義を再認識させられるような内容でした。
全体としては過去問ベースの問題や過去問そのままの画像も多く、過去問の重要性は依然として変わりません。しかしながら、従来よりも細かい知識を問われたり、新たな問われ方をしたりと、雰囲気で覚えている程度の知識では太刀打ちできない問題も散見されました。その結果、選択肢を絞り込み切れず、自信をもって解答できない問題が複数ある状態で解き進めねばならないような状況となった人も多いでしょう。また、禁忌とされる内容から作られたであろう選択肢もいくつか見受けられ、「現場で絶対にやってはいけないことを確実に除外できるか」という点でも頭を悩ませたことかと思います。国試は長丁場の試験で肉体的に厳しいものですが、今回の国試は精神的にも厳しい戦いだったかもしれません。
とはいえ、一部の難問を除けば、しっかりと問題文を読み、臨床文などから状況を的確にとらえ、「まず」、「優先的に」など何が問われているかを把握し、判断することができれば解ける問題と、過去問ベースの平易な問題で構成されていました。時間をうまく使いながら確実に正答を導くことができれば、自ずと合格ラインにたどり着けるような問題群でした。
今後も、習得すべき知識の範囲をやみくもに広げたり掘り下げたりする必要はなく、明確にレベル分けされた令和6年版医師国家試験出題基準(ガイドライン)に沿って、取捨選択すればよいと考えます。出題者が「知っておいてほしい」というレベルを理解し、確実に習得することが重要であり、この点では予備校教材の活用にメリットがあります。
基礎~CBT~臨床医学の流れから実際に医師になるための大きなステップとして、必要な知識を問う集大成が国試であるということを印象づけたような第119回医師国家試験。あらためて、医学部入学時からのすべての知識は、その先に医師に繋がっているということを意識しながら学習する大切さは、今後国試を受験する皆様へのメッセージといえるでしょう。
2025年2月11日
MEC 医学評価センター国試分析チーム
(メック講師・企画部・制作部)